血圧は一律ではない
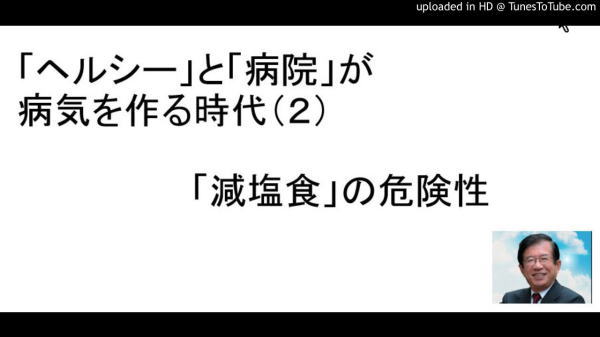
前項からの続きですが、ある人の血圧が午後2時に医師の前で測定した155というのは適当であり、体は正常だったとしても、「一律に血圧を決める」という医学に頼る医師がいるわけで、指示された通りに、間違えであってもその日から減塩食を食べるようにしたとします。
すると体に必要な塩分が不足するので血圧が下がり、気分が悪くなります。疲れやすくなり、風邪もひきやすくなります。立ちくらみがするなどの症状が出ることもあります。
この場合を考えてみると、「減塩食」というのは、とてもではありませんが「ヘルシー」ではなく、むしろ「病気を作るための食事」になってしまいます。ひょっとしたら、その男性が次に病院に来るのが医師は楽しみなのかもしれません。
正しい流れは、「医師はその人の正しい血圧を決定すること」、「測定した血圧が正しい血圧より高い場合は、減塩食はヘルシーとなる」、「測定された血圧がたとえ高くても、それがその人の正常な血圧ならそのままの生活を勧める」ということです。
単純に一律で減塩食がヘルシーなのではありません。求められているのは「血圧を正常に保つ食事がヘルシー」ということです。私は、医師が正常な血圧を知らずに、よく人に減塩食などを勧めていると驚いてしまいます。
また、減塩して血圧が下がると、血流量が減ってガン、腎臓病、うつなどを発症する危険性が高くなることを指摘したいと思います。血の巡りというのは非常に大切で、昔でも「冷やしたらダメ」、「温泉にゆっくりつかると血の巡りがよくなって病気が治る」など多くのことが経験上知られています。現代的に言えば「血の巡りを良くして、免疫力を高める」ということを指しているのでしょう。
せっかく心臓が動いてやや高い血圧を維持し、血流を良くしている状態なのに、わざわざ減塩食で血圧を下げて血の巡りを悪くする必要はないでしょう。